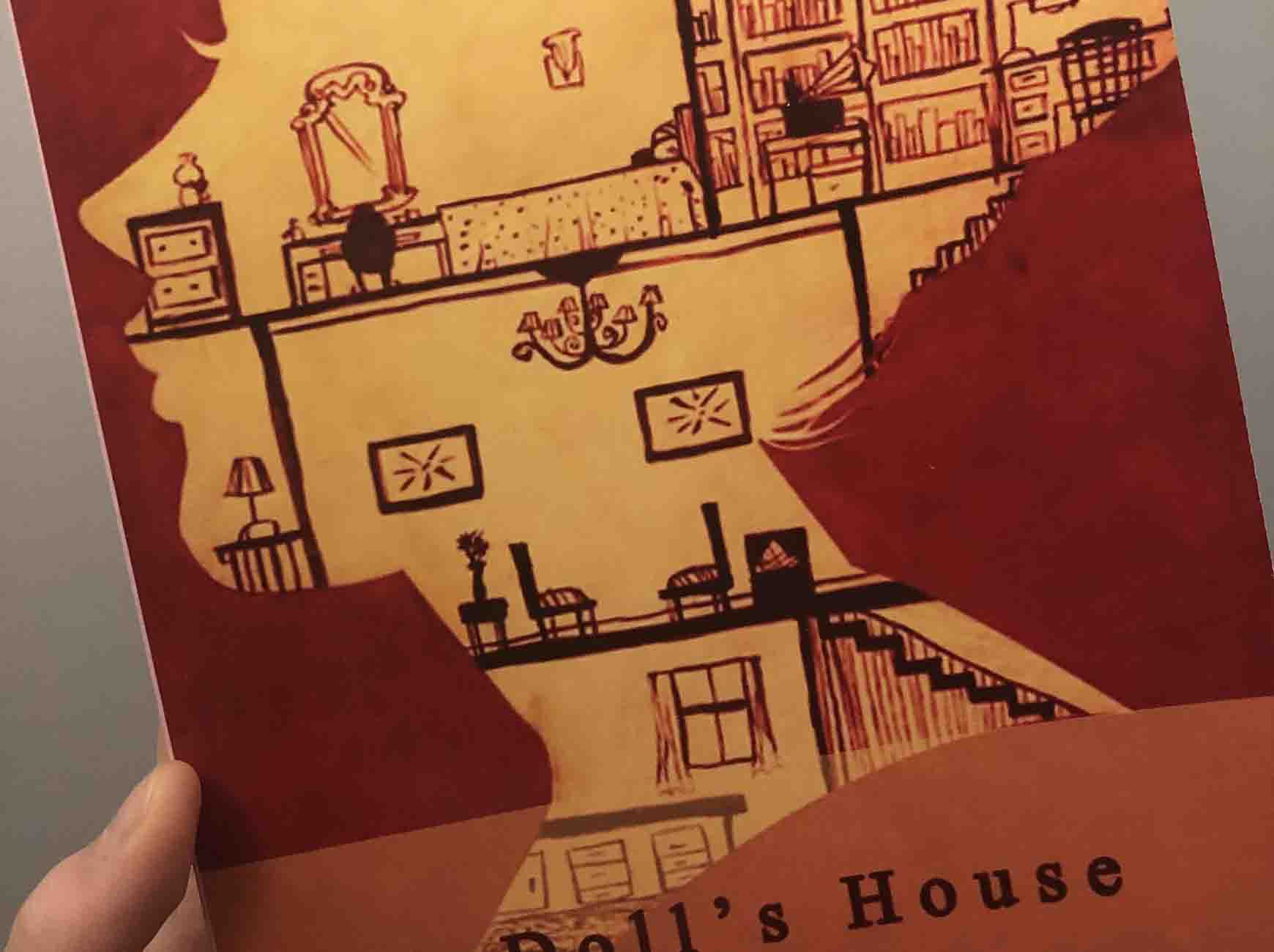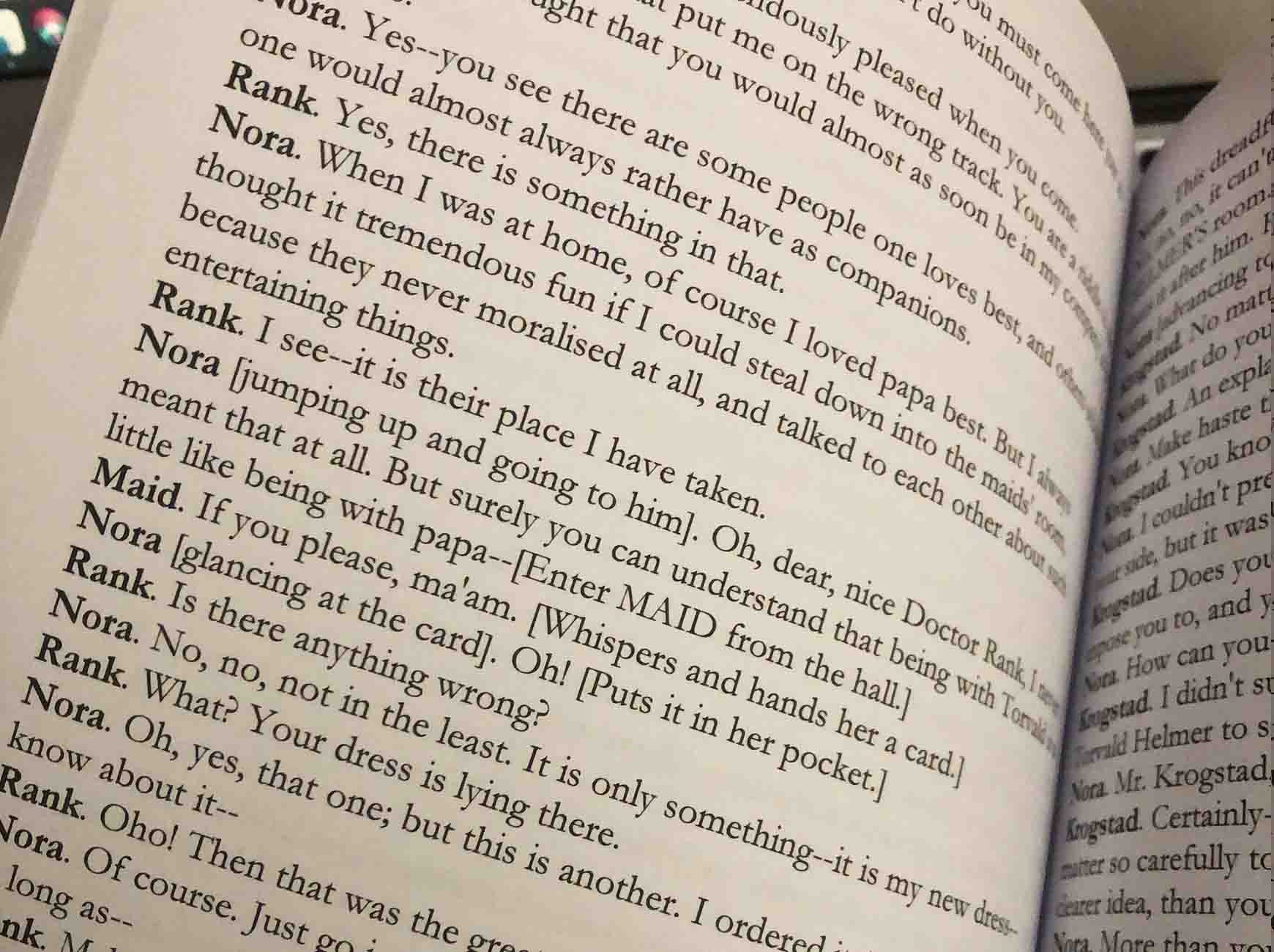国際バカロレア校、ある日の英語の授業内容を一部公開!DP履修生が日記形式で紹介します。

DP履修生が語る、国際バカロレア校のリアルな日常
- 名前
- 木村紗羅/Sara Kimura
- 所在地
- パリ
- お仕事
- International School of Paris 学生
- URL
- International School of Paris
【DP履修生が語る、国際バカロレア校のリアルな日常】国際バカロレアについての基本的な内容、求められる人物像などについては、これまでの連載で存分に語ってきました。今回からは、より具体的な授業内容や、国際バカロレア生の日常について、日記形式で綴っていきたいと思います。
2月10日 英語(Language and Literature - English A)のクラスで
先週でスピーチを分析するユニットを終え、今日の授業からは戯曲のことを学び始めました。具体的な作品名はヘンリック・イプセン作『人形の家』です。
まず、新しいユニットを始めるときの常例として、先生が教室のスマートボード(電子黒板)に、そのトピックに関しての質問を映し出し、隣の人と話し合うよう指示。
質問内容は、通常のテキスト(文章)と戯曲のテキストの違いでした。
「戯曲って役者さんの解釈を通して観客に届くから、2回解釈の段階を経ると思わない?」「あぁ確かに役者さんと観客の2段階ね」などと5分ほど話し合い、手を挙げてクラス全体に共有しました。
たった5分の話し合いの後に、様々な意見が教室を飛び交うなんて、さすがマルチタスクに慣れている国際バカロレア生だなと感じました。
私が国際バカロレアを履修し始めた頃、発言すると同時に頭をフル回転させることに手こずりましたが、3年半経った今では、その能力がかなり磨かれたのではないかと思います。
皆での意見交換の後は、先生が『人形の家』の基本情報・背景を説明。原作のノルウェー語で書かれた文章と、英語に訳された文章を照らし合わせることのできるプリントに目を通しました。
私たちのクラスにノルウェー語を話せる生徒はいませんが、アルファベットで書かれている文章からは、1、2語は読み取ることができます。
そこでまたディスカッションの時間です。「何通りか表記された英語訳、一人一人どれが好きか選んで、その理由を教えて」と先生。
じっくり文章を読んでみました。最終的に受け取るメッセージは同じでも、少しのニュアンスで作品の雰囲気が大きく変わり、バイリンガルの私にはとても興味深かったです。
プリントを参照したり、先生がスマートボードに映している質問について考えてディスカッションをし、それをクラス全体で話し合う。このような流れは国際バカロレアの授業でよく見る光景です。
授業の最後に、先生が皆に質問を尋ねられました。「通常のテキスト(文章)と翻訳された戯曲のテキストの違いとは?」
今日学んだことを組み合わせながら、数段落の説明文を書きました。その文章は、学習者ポートフォリオ(卒業に必須なメモ的なもの)に加え、授業終了。
<連載概要> 「国際バカロレアの日々の学び」を実際の学習現場からお伝えする、木村紗羅さんの体験日記はこちらより
DP履修生が語る、国際バカロレア校のリアルな日常