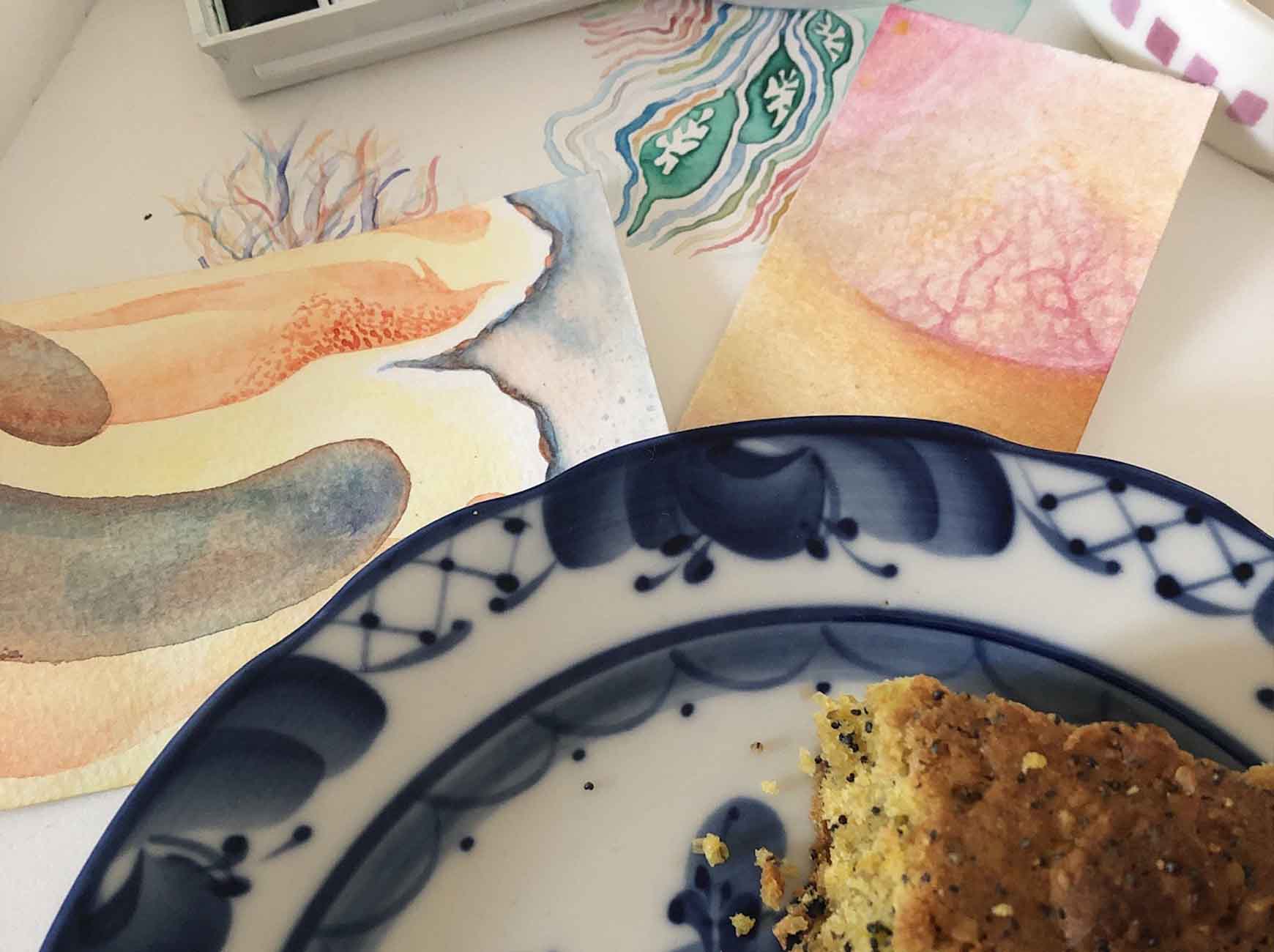国際バカロレア・DP最終学年の11月。IAのレポート提出と忙しい毎日。

DP履修生が語る、国際バカロレア校のリアルな日常
- 名前
- 木村紗羅/Sara Kimura
- 所在地
- パリ
- お仕事
- International School of Paris 学生
- URL
- International School of Paris
【DP履修生が語る、国際バカロレア校のリアルな日常】
11月25日
DPの11月はとにかく忙しい月になりました。まずひとつの山場は、IA(Internal Assessment)のレポートの提出。
以前の記事に書いたように、私の生物学のIAは塩分濃度とイースト菌の発酵の関係について研究するものだったので、完全に実験ベースのものでした。一方で、数学のIAは、「3Dプリントで作成する、弟にとって最も理想的なおにぎりが作れるケースの寸法は?」という曖昧なリサーチクエスチョンで、図形を書き、データを集め、計算をして結論まで持っていく内容となりました。
数学のIA課題を具体的に説明しますと、まず、母が作るおにぎりの重量と弟の残してくるおにぎりの重量の5日間の平均値を求めました。それを元に、弟がご飯を残さないでいられるおにぎりの体積が出たので、その数値を固定し、三角柱、俵型、そして球体のおにぎりケースの最小の表面積の寸法を計算しました。表面積が最小=3Dプリントで作成した時のコストも最も少ないので、それを「理想的」としたほか、弟の口のサイズに対する最も食べやすい形、通学用バッグの底に入れた場合に余分な空間を取ることが最も少ないものがどれかを分析していきました。
先生にはアイデアが個性的だから面白いと評価していただけました。
そして二つ目の山場は、大学受験用のTOEFLの試験でした。
TOEFLの試験は、今回で2回目。初回はフォーマットに慣れておらず、準備不足だったため、100点以上は取れたものの、優秀な帰国子女の方々との受験になることを考えて、もう少し上を狙いたいなと思う結果だったのです。
2回目はまだ最終試験結果が出ていないのですが、リーディングは満点で、リスニングは点数が確かに上がっていたので(テストが終わるなりその2セクションの結果は画面に表示)一安心です。
TOEFL対策としては、問題形式を把握すること、そしてリスニングはもちろん、ライティングとスピーキングで必須となるメモ取りのコツと自信をつけることだと感じました。
私の場合、パッセージを聞き取りながらメモを取ると、集中力が分散してしまい、最初はとても手こずっていました。ですが問題形式を覚えると、メモを取るべき部分とそうでない部分を分けることができるようになります。余計な箇所を省けば、より効率良く問題に答えられるはずです。
大半の大学は、国際バカロレアのプログラムをすべて英語で受けてきた人はもちろんのこと、English Aを受けていれば、TOEFLの点数を求めることはほとんどありません。ですが、私の場合は、TOEFLが重視される日本の大学を受験するので、日本から海外の大学への進学を目指す多くの学生の方々と同様に、ここでしっかり点数を取っておきたいところです。
在校生に聞いた点数の目安は、当然学部によって違うのですが、9月入学で全英制に関しては100点以上、海外経験が長い人は105点以上とっているそうです。なので、一般的な目安はやはり最低でも100点以上だと思います。
国際バカロレアを履修している学生の大半は、国際バカロレアが世界中で通用することが理由で受けています。そのため、進学先もとても多様です。
11月初頭ですでに第1志望のIT校に受かったクラスメートは、オランダでITエンジニアの道を進む予定ですが、イスラエルやフィンランドの友だちは兵役に行く準備をしています。オーストリアで建築、日本で看護学、パリでファッションを学びたいという人もいれば、自分探しをするためにギャップイヤーを取る友だちや、ニューヨークでブロードウェイ女優になることを目指してシアター学校を片っ端から受けている友だちもいます。
大学の先も見据えてライフプランを立てている生徒が多くて、とても良い刺激になっています。
<連載概要> 「国際バカロレアの日々の学び」を実際の学習現場からお伝えする、木村紗羅さんの体験日記はこちらより
DP履修生が語る、国際バカロレア校のリアルな日常