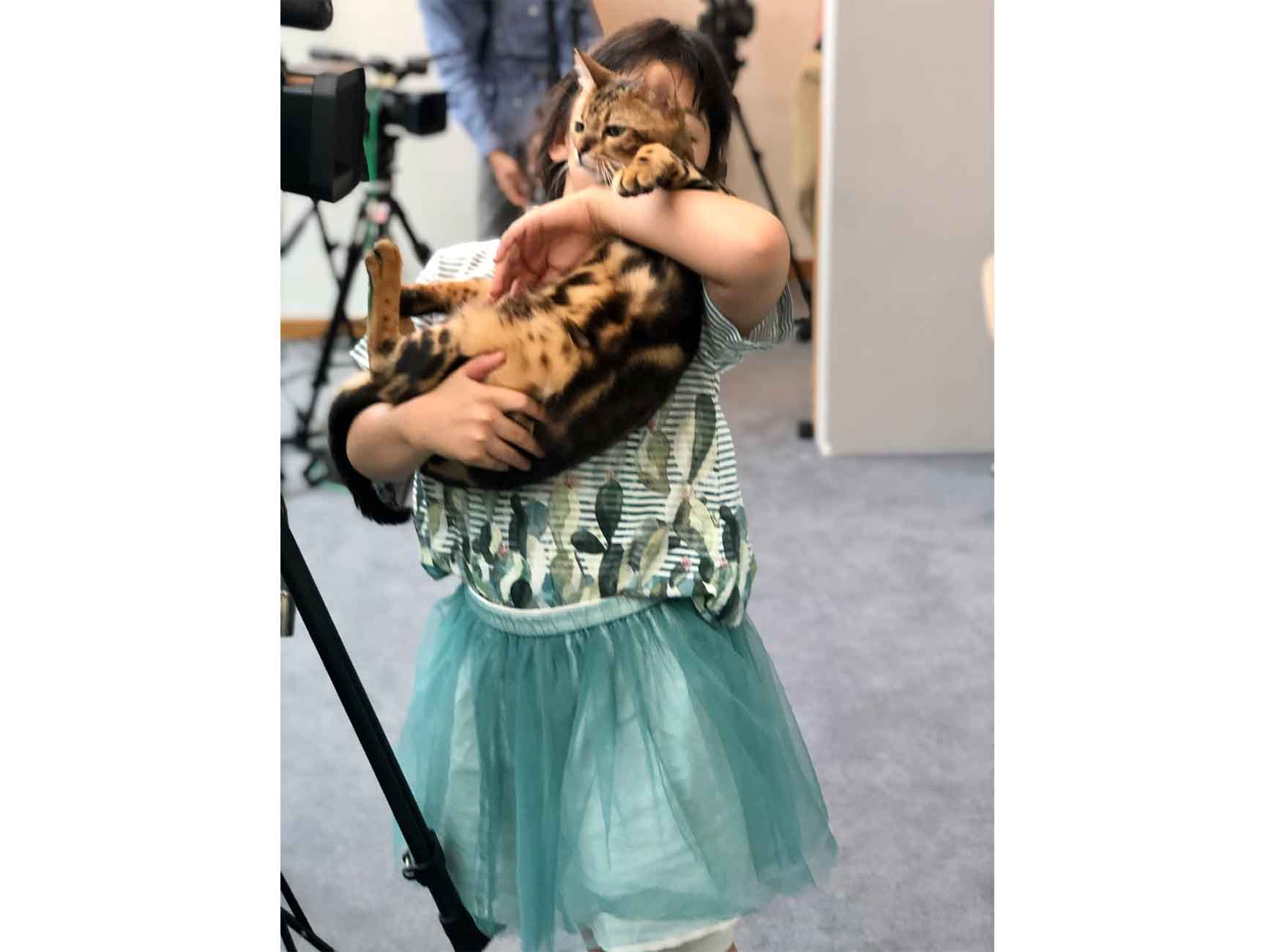自意識も反発も、水色をめぐる自己表現のなかに

子どもの未来をクリエイトする、国際政治学者の個性派子育て
- 名前
- 三浦瑠麗 / Lully Miura
- 家族
- 3人(10歳女の子)
- 所在地
- 東京都
- お仕事
- 国際政治学者
- URL
- 三浦瑠麗(@lullymiura) Instagram
【子どもの未来をクリエイトする、国際政治学者の個性派子育て】
ちいさいときから水色が好きでした。ピンクは自分にあまり似合わない気がしていたからです。特段ピンクが嫌いだったわけではないし、数十年前のことですから、「"女の子がピンクで男の子が水色"というステレオタイプはいかがなものか」という、意識の高い話ではまったくありません。単に、水色の美しさに心惹かれていたのです。
水色と一口に言っても、いろいろ。空色、白藍、藤色、縹色(はなだいろ)、納戸色、浅葱色(あさぎいろ)、勿忘草色(わすれなぐさいろ)。そして、ライトブルー、スカイブルー、ターコイズブルー、パウダーブルー、ベビーブルー、ティファニーブルー、マヤブルー、セルリアンブルー、ブルーグレーと、それこそ1000もの異なる色合いがあります。
わたしは中でも、藍を含んだ明るい縹色や、晴れた日の深く青い空のような紺碧、そして、天使が降りてくるときの雲を縁取る空のようなパウダーブルー、マヤブルーが大好きでした。
6歳くらいのときでしょうか。ふだんなかなか行かないデパートのとある売り場で、淡い水色の薄いシフォン地を重ねた共布のサシェ付きのドレスをみたとき、わたしは強い憧れにかられて、そこから離れられなくなってしまいました。そのあとみんなでうちに帰ってから、大好きだった茅ヶ崎のおばあちゃんにこっそり話したのです。直截的におねだりしたつもりはありません。でも、もしそれが何らかの入り組んだ過程をとおって自分のものになったら......。わたしの言葉のなかに、強烈なもの欲しさが感じられたであろうことは確かです。
祖母はふんふん、と聞いていて、一言「買ってあげようね」と言ってくれたのですが、祖母が母にその話を切り出したあと、わたしのちいさな夢は当然のように潰れました。そんな高いものをおばあちゃんにおねだりするなんて、と正面から大目玉を食らった方がまだましだったかもしれません。そうではなくて、もっと回りくどい言い方で却下されたような記憶があります。結果わたしは、ありもしないパーティーにしか着ていけないようなひらひらとした服を欲しがる自分へのやましさを、持たざるを得なかったのでした。キリスト教的な禁欲教育が染みついていたせいでしょうか。
幼いころに読んだアンデルセンの絵本『赤いくつ』。虚栄心から教会へ履いていった赤い靴が脱げなくなって、木こりに足を切り落とされるまで町中を踊りつづける少女の姿がどうしても頭から離れなかった。いわさきちひろが描いたはかなげな挿絵は、グロテスクなはずのシーンでも見入ってしまうような、悲しげな少女の顔が印象的です。葬儀に赤い靴を履くことは、そんなにも呪われるべき罪なのだろうか。幼いわたしにしみ込んだ道徳では、女は初めから罪深い生きものであると告げていました。
ちいさい頃に読みあさった世界の少女名作文学では、いずれも思慮深い少女が誘惑を乗り越えて、真の愛を勝ち取るまでのお決まりのパターンが描かれていました。たいてい、少女たちは美しいのに自らの美しさに気付かない。彼女たちは外見の華やかさではなく、つつましい幸福を選びます。『若草物語』では、長女のメグが着飾ることの誘惑を遠ざけ、貧乏な家庭教師と結婚する。次女のジョーは大富豪の跡取り息子のプロポーズを断り自活する道を選ぶ。でも、今から思えばこうした物語そのものが、すでに女の外見に関する強烈な自意識に絡めとられたところから始まっていました。
なぜ理想の男性と出会い、その人に愛されることが究極のハッピーエンドなのか。こうした物語は、誰しもが愛されたいという欲望や、容貌をめぐるコンプレックスから自由ではないということを、逆に教えてくれます。外見が美しくなくても、ある日魔法のようにあらわれた人と恋に落ち、愛される。もちろん、これは女の子だけでなく人間に共通した欲望です。
それでも、女はとりわけ、容姿に強迫的なまでの自意識を持ちます。というより、持たされているのかもしれません。小さいころから周りと外見を比べられ、まるでそれ以外のことがほとんど価値を持たないかのように全否定される経験をする。美しい赤い靴に憧れる気持ちは当然なのに、罪悪感を持ってしまうのも、あるいはそんなものは虚飾でありくだらないと強く拒絶するのも、ほぐしがたく捻じれてしまった自意識からきています。
だから、女の子に当然のようにピンク色をあてがうことへの反発は、おそらく単純に「いやわたしはブルーが好き」とか「そうじゃなくて黄色が好き」といった、好みの問題にとどまらない根深さを持っているのだと思います。
それは、フリフリしたピンクのドレスが似合ってしまうクラスで一番かわいい子に対する反発であり、自分だけは特別でありたいという気持ちであり、男子に求められたいし綺麗でいたいけど、それでも中身で判断してほしいという複雑な思いからくる自己表現のあらわれなのです。
わたしの思い出のなかの水色は、やはり自己愛。ほかの人とは違う自分でいたいという夢でした。デパートのつるしの洋服は大量生産品でしかないのに、そんなありふれた水色のドレスでもってして、ちいさなわたしは唯一無二に自分を着飾ろうとしたのでした。
このように、女の子が追い求める"自分らしさ"は、ひとりひとり違うつもりでいながら、最後にはまったく周囲と区別のつかない純白のウエディングドレスに結実します。それが、唯一無二であろうとしながらも、「人並みの幸せ」を手に入れたいと思うわたしたちの抱える矛盾なのです。いまでこそ、結婚式に白いドレスを着なくてもよかったと思うのですが、それは後知恵。いちどやってみないと、人間は納得できないのかもしれません。
愛されることへの渇望から、わたしたちが自由になる日は来ないのかもしれません。それでも、肩をいからしていた若い時分よりは、幾分自由に水色を愛でることができるようになりました。いちずに純粋ではなくなったからこそ、そしてあまり自己中心的でもなくなったからこそ、すべてのものを欲しがらなくなった。
あたり一面に咲く勿忘草は、永遠に身につけることのできないその場限りの美しさに満ちています。美しいものを所有しようとするだけではなく、ただ愛でる。ただ、見に行く。そうなってはじめて、自由に色を楽しめるようになったのではないか。そんな気がします。
〈三浦瑠麗さん連載〉
子どもの未来をクリエイトする、国際政治学者の個性派子育て