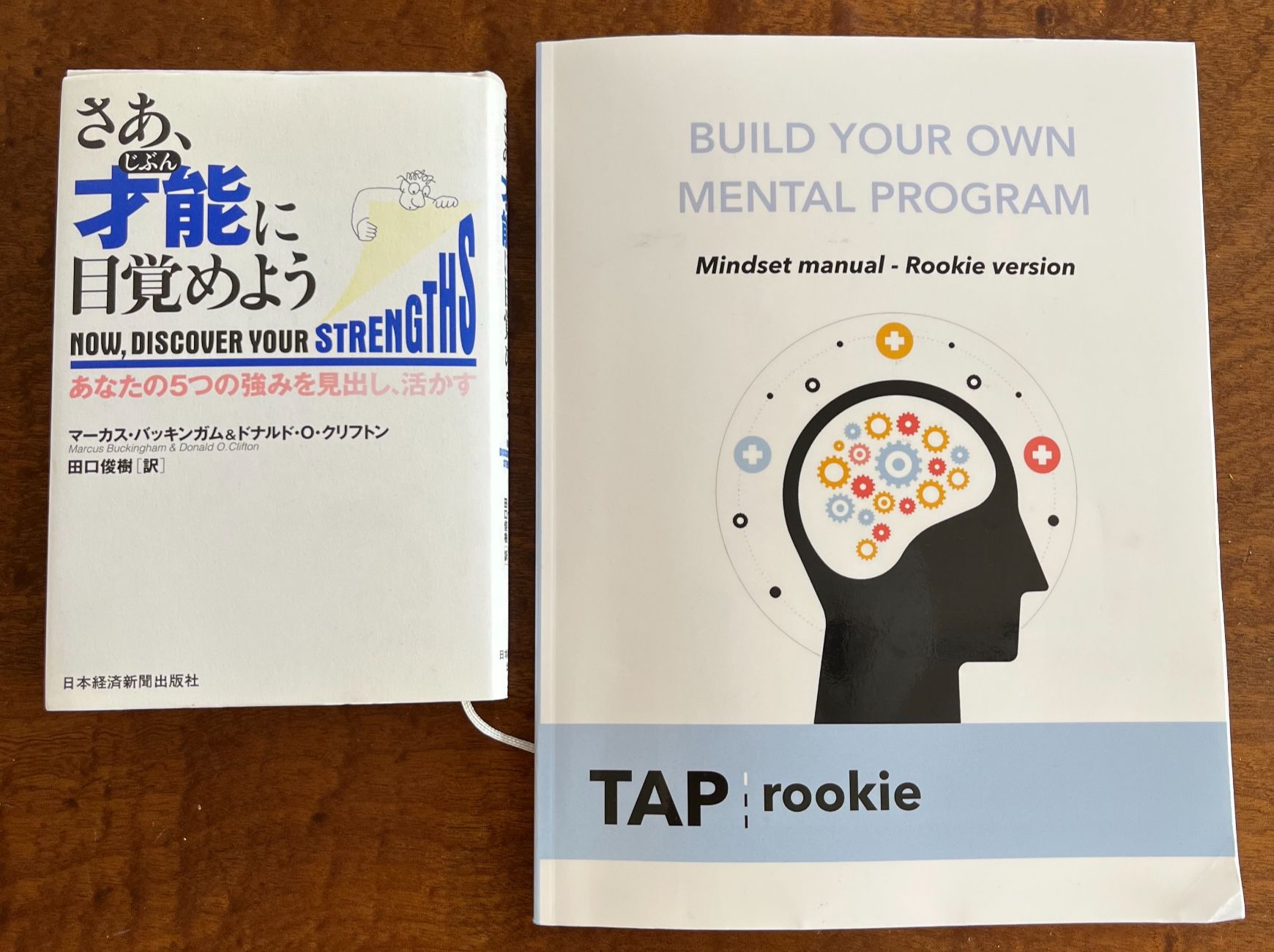「子どもの嘘はかわいい」。自己肯定感を高める令和の子育て

「子どもの好き」が最大のモチベーション!な国際派子育て
- 名前
- 佐久間麗安 / Rena Sakuma
- 家族
- 4人 (11歳男の子と9歳女の子)
- 所在地
- 東京都
- お仕事
- Bright Choice編集長
- URL
- Rena Sakuma (@renanarena0513) Instagram
【「子どもの好き」が最大のモチベーション!な国際派子育て】
「子どもの嘘はかわいい。」
最近になって、そう思えるようになってきました。
私も、夫も、大変に厳しい親に育てられました。
「親のいうことは絶対」だったし、親の正義から逸れることをすれば、ひどく叱られました。躾にしても、勉強にしても、正直に生きるということにしても、「ちゃんとした人間に育てる」、そんな親の問答無用の強い正義感をひしひしと感じて育ったものです。今の私たちがあるのは、実直で真面目な両親のおかげです。
「われわれ人間は、『善は悪の対極にあるもの』という考えに固執し、何世紀にもわたって欠点や弱点にとらわれてきた。」
強みに基づく人材開発サービス、クリフトンストレングス(ストレングスファインダー)で有名なGALLUP社のマーカス・バッキンガム&ドナルド・O・クリフトンは、共著『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう』でそういっています。なるほど、多くの職場の人材開発で取り入れられているこの概念を子育てに当てはめて考えれば、子どもの自己肯定感を高めるヒントがありそうです。
「嘘は泥棒の始まり」、という言葉があります。「嘘をついたらダメ!」と自分もよく子どもにいっていました。いま思えば、それはきっと、私たちの受けてきた「昭和の教育」のすりこみ。嘘をつけば悪党とでもいうように、私たち親は、善と悪が対局にあるということに囚われて生きてきました。私たちも、子どもの頃は叱られるたび「自分はダメな子なんだ」、と思って育ちました。人間の感情の、白でも黒でもないはっきりしていない部分と向き合うことの方が、一人の人間を育てるために大切だというのに。
「子どもの嘘はかわいい。」
なぜって、子どもの嘘に悪意はないからです。歯磨きが面倒だったから、歯磨きしたよ~っていってしまったり、あるいは、自己防衛でつい嘘をついてしまったり。だから、可愛いうちに認めておいてあげた方が良いのかもしれません。当然、社会に出れば、詐欺や隠ぺいなどには刑罰が存在します。しかし、かわいい子どもが大したことのない嘘をつくうちは、面倒くさがったり、本当のことをいうのを怖がったり、そんな未熟で柔らかい部分と寄り添ってあげることの方が、親の役割として重要なのではないでしょうか。
なぜなら、そうして生まれる親子の対話によって、子育てが前向きになるから。子どもが自分の内面と向き合って、子ども自身が"気づく"ことで、自ら成長し、「自分は面倒くさがりだけど、歯は磨こう」、「怖いけれど、本当のことは伝えよう」という自己認識のもとに挑戦できる。そうして、白も黒もそうでない部分もひっくるめて、自分を好きだと思えるようになるのでしょう。それは親にとっても子どもの気持ちを知るきかっけになる。「~はダメ!」という、子どもを否定するような正義感の押しつけは、親子の対話を阻み、思考停止をもたらします。
日本の子どもの自己肯定感が圧倒的に低いのは、規範と同調圧力の強い社会だからなのでしょう。お受験のルールや厳しい学校の校則もあって、行儀やたしなみといった社会規範がきつい。ハイコンテクストな日本社会は、戦後の大量消費社会を築くことに成功し、私たちに豊かな生活をもたらしてくれました。しかしこれからは、そこから外れた世界の多様な人々と上手く付き合いながら生きていかなければいけません。
女の子の子育ては特に注意が必要なように思います。良くも悪くも、「しっかり者」の女の子は、内面の成長が早く、自意識も高い。ジェンダーの意識が芽生えるのも早いから「女の子であること」のしがらみもある。そんな女の子社会は特に、ファッションや遊びの嗜好など、同質であることを求められたり、規範を逸脱すると後ろ指されることも多いですね。
「○○しちゃダメなんだー!」なんて強い口調で攻撃されることもあったり、「仲間はずれ」のような友人関係のトラブルなど、いろいろと難しいことがあります。
悪気はない子どもたち同士のことですから、本当は深く考える必要はないのに、まだ小さな子どもには大事に感じられてしまう。一番可哀そうなのは、自分が悪いと思ってしまうこと。私も幼少の頃にそんな経験を何度もしました。
小学校3年生の娘も、女の子社会の難しい部分を知っています。私は娘に、女の子グループから外れてみたり、距離を置いたっていいと伝えています。「何か嫌なことをいわれたら、ため込まないでママに伝える」というのが約束。「え~!そんなこといわれちゃったのかー。気にしない、気にしない!」なんて頷きながら、私は相手に悪気がないということや、娘にも非がないということを一緒に確認してみる。
娘が逞しいのは、「○○ちゃんのこと苦手なんだけど、本音はいわないの。○○ちゃんがキツくいうのは~のせいじゃないんだよ」といえること。それは、善悪の二極で人を判断しない、彼女のとても良い部分です。白でも黒でもない部分を知るだけで、人間は強く優しくなれるのかもしれません。
「嘘も方便」なんて言葉がありますが、大切なのは、「嘘をつかないこと」ではなくて、誰かを傷つけないことであったり、平穏を保つこと。ときにいがみ合う大人社会を見ていれば、人間社会にとって正義を貫くよりもっと大切なことがありそうです。
多様化する社会で、もっと個性を尊重する教育が必要であると、日本の学校でも謳われるようになりました。一番大切なのは、まず善悪で捉えられない人間味ある部分を、私たち親が認めてあげること。自己肯定感が圧倒的に低いといわれる日本の子育てで、いま最も大切なことかもしれません。
一方で、規範の強い日本にも、良い部分がありますね。
「おさない、かけない、しゃべらない、もどらない」、学校の消防訓練で耳にタコができるくらいいわれたから、大震災のあったときも日本人は落ち着いて協力をし合って緊急事態を乗り越えることができました。ただ盲目にルールに従うのではなく、子どもたちには日本人であることに誇りを持って、多様な世界で活躍してほしいものです。
控えめに見える日本人が世界に羽ばたくには、もちろん次世代教育に必要とされる立派な学校設備やプログラミングやバイリンガル教育といったハード面も必須です。しかし、子どもと親、子どもと先生、子どもとコーチなど、子どもの築く人間関係の中で繰り広げられる様々な対話というソフト面にこそ、真の知性の土壌があるのではないでしょうか。
〈佐久間麗安連載〉
「子どもの好き」が最大のモチベーション!な国際派子育て