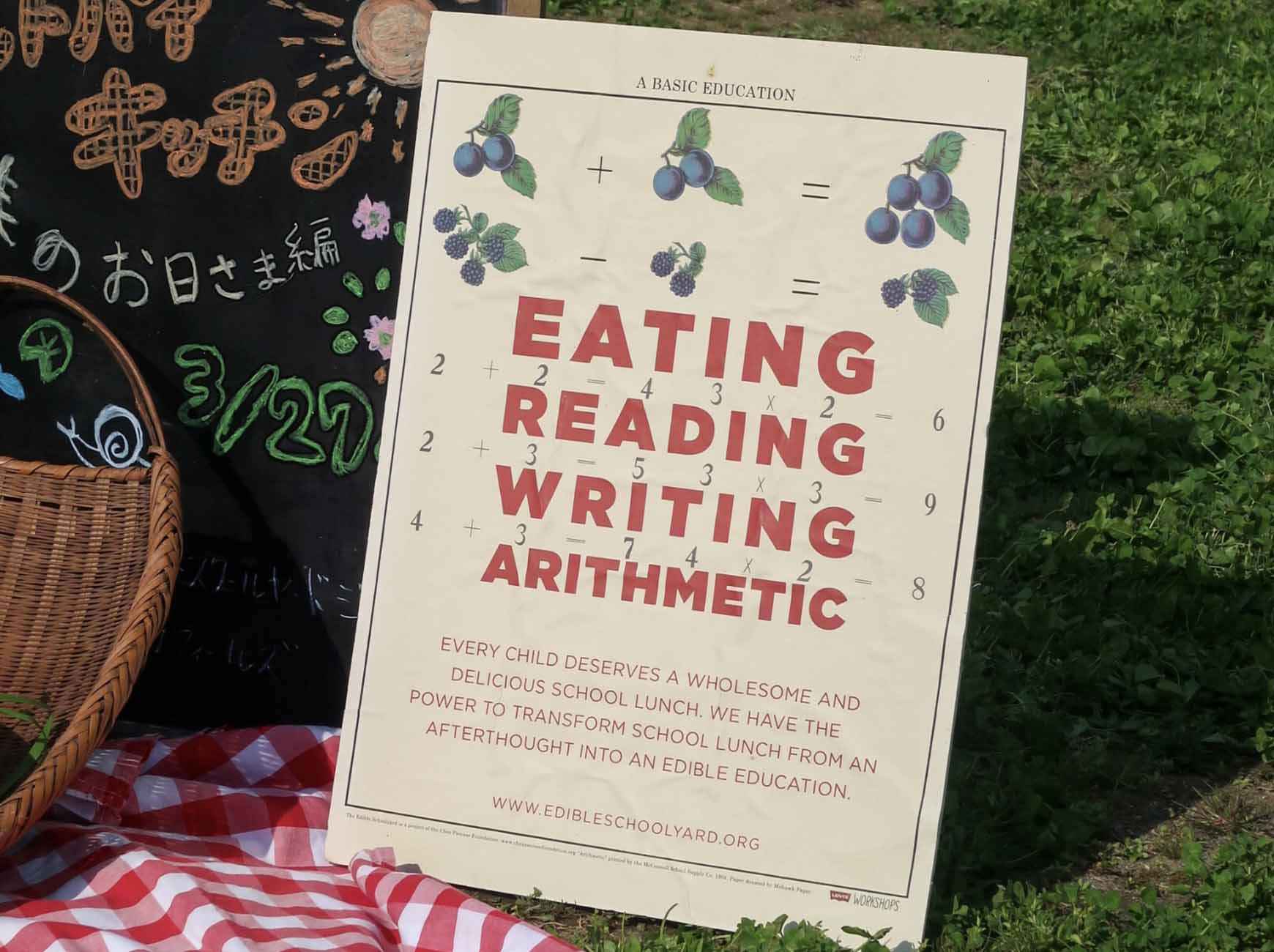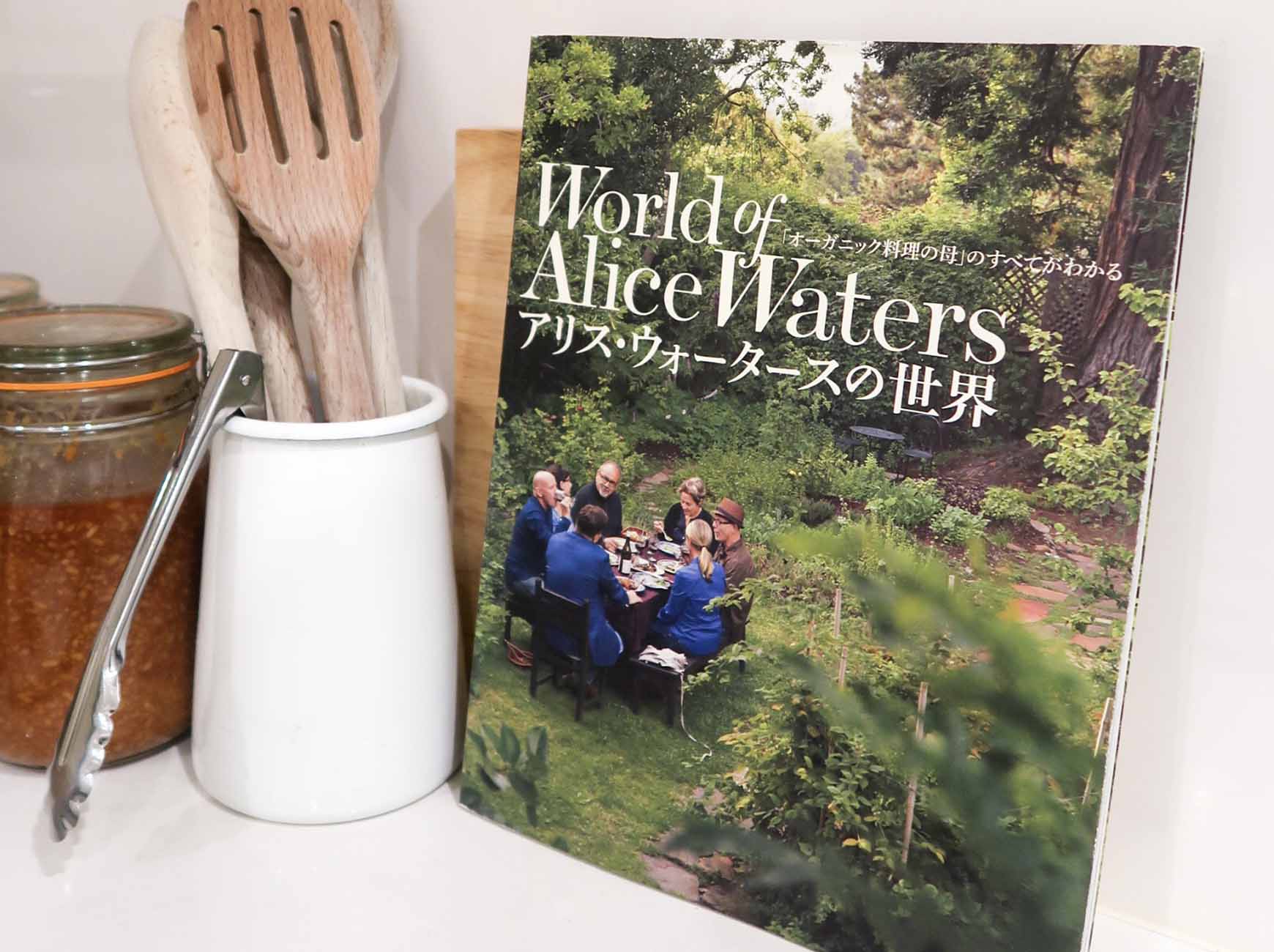子どもの話を最後まで聞く。意外とできていない対話の基本。

「わたしはわたし」自尊心を育む子育て
- 名前
- 浅倉利衣 / Rie Asakura
- 家族
- 4人 (8歳と5歳の女の子)
- 所在地
- 東京都
- お仕事
- コラムニスト
- URL
- Rie Asakura (@rie_asakura) Instagram
この一年で、個人的に感じる大きな変化があります。
それは、「途中で口をはさまずに最後まで話を聞く」ということが自然とできるようになったこと。加えて、先入観などからジャッジしてしまうこともなくなりました。
ものすごく当たりまえのようで、思い返すと意外とできていなかったなと思うことでもあります。
たとえば子どもや他人が、何か困ったことがあったり不満があって話してきた時。
「でもそれはこうした方いいんじゃない?」というアドバイスと共に途中で遮ってしまったり、イライラして最後まで聞けていなかったようなことって多々あったなと。
ではなぜ最後まで話を聞けなかったり、話を途中で遮ってしまうのか。
私の場合は、自分が自分自身の心の声を、なんのジャッジもせずに出させてあげて、そして全て聞いてあげられてなかったことにありました。
「なんか嫌だな」とネガティブだと判断した感情を味わいきる前に蓋をして、「もっとこうすればいいのでは」「なんとかしなきゃ」とすぐに対策や改善策を考えがちでした。そして、同じことを子どもや相談してくれた相手にもしてしまっていたんですよね。
聞いているようで、聞いていない。途中から「自分の物差し」がムクッと顔を出し、ジャッジが始まっている。
つくづく、子どもは、他人は、自分自身の内側を投影して見せてくれているのだと感じます。
でも、昨年精神的に大きく揺さぶられたことをきっかけに、自分の心と体の声をただコツコツコツコツ聞き続けてきた結果、子どもや他人の声も、自然となんのジャッジもなく最後まで聞けるようになっていることにある時ふと気づきました。
と同時に感じるのは、私が口をはさまず最後まで話を聞きまるごと受けとめることで、子どもや相手も自分の言いたかったことを全て出し切れて、結果として解決している場合も多いなということです。大人でも、話を聞いてもらえただけでスッキリしてしまうことありますよね。
また、「聞いてもらえた」「わかってもらえた」という安心感が、相手の顔色を窺いすぎず、「言いたいことを全部話してもいいんだ」という自信にも繋がるような気がしています。
まだ感情を表現する言葉が身についていない小さい子の場合は、たとえば泣きたい時は我慢させず思いっきり泣かせてあげて、「かなしかったんだね」「さみしかったんだね」「くやしかったんだね」などと、通訳しながら、感情と言葉を繋いであげる。
5歳の次女もだいぶ言葉が達者になってきましたが、それでも自分の感情を上手く表現できなさそうな時は、そんな風に感情をおもいきり出させてあげた後、通訳することを心がけています。すると、泣きながら、「うん、うん」と首を縦にふって、その5秒後にはケロッと泣き止んで、抱っこしていた腕から自分からおりて、また元気に飛び出して遊び始めたりします。今回のメイン写真を撮った1分前も、まさにそんなことが起こっていました。
「自分の心の声が言いたいこと・感情を全て出す、そしてそれを自分自身でまるごと受けとめてあげる」。
なんだか呼吸と一緒ですね。息を十分に吐かないと十分に吸えない。
つまり、言いたいことも言えなければ言えなくなるほど、聞く・受けとめるキャパシティもどんどん小さくなっていく。
自分との対話、そして自分が自分を認め信頼関係を結べるようになった時に、自然と子どもや他人にもできるのかもしれません。今のところこれに尽きるなと感じていますし、今後もし、「あ、子どもや他人をジャッジしているな」「話をまるごと聞けてないな」と感じた時があったら、まずは自分をかえりみたいと思います。
〈浅倉利衣さん連載〉
「わたしはわたし」自尊心を育む子育て